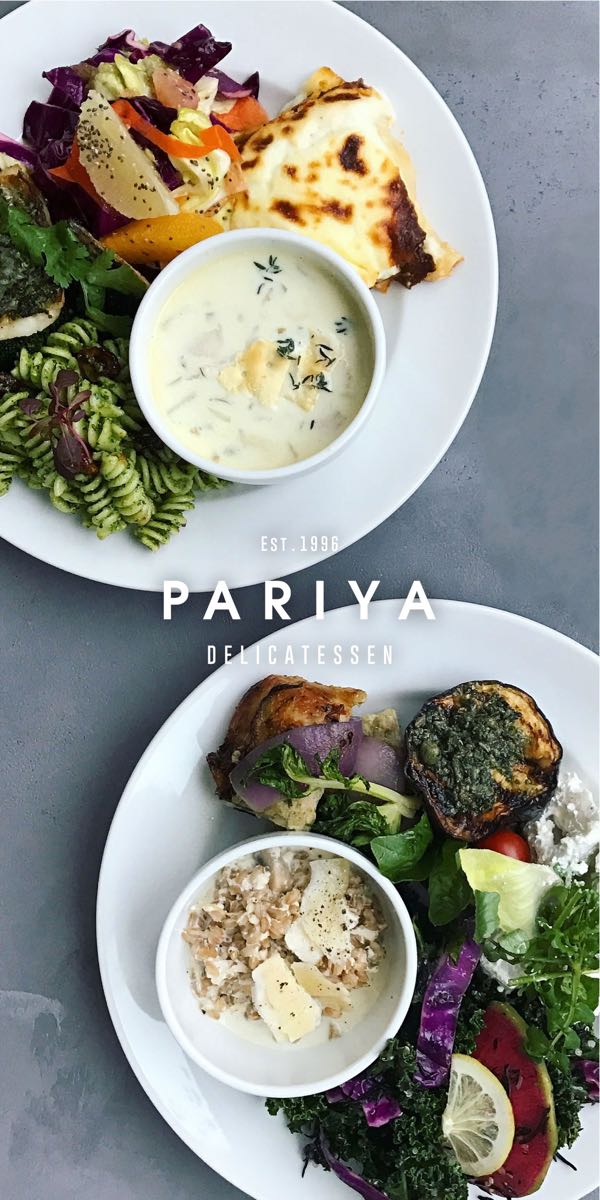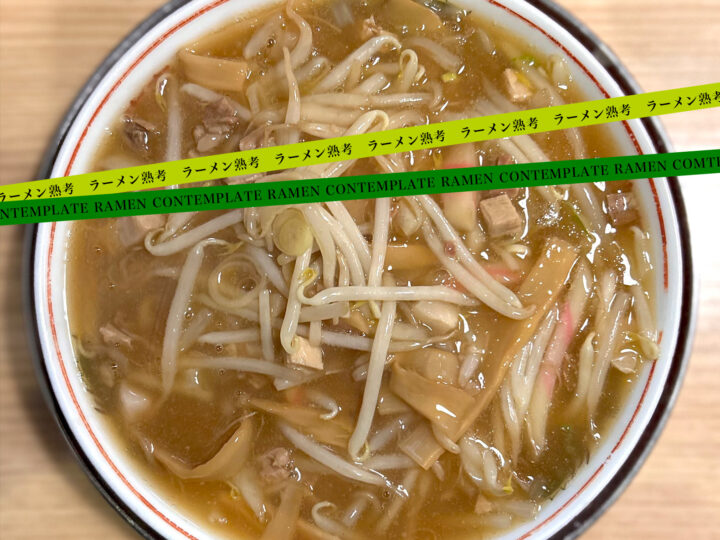旅とインド料理
002 忘れられないコルカタのビリヤニ
ビリヤニは、日本で言うところのラーメンのような寿司のような、特別なご馳走でもあれば労働者の燃料的な存在でもある。ムンバイのレストランで肉体労働をしていたとき、疲れた身体で夜中の1時頃に無心でビリヤニを食べていた時期もあった。
カレーのルーツを探るため、インドやその周辺国に十数回渡航してきた。現在は大学院でインドに関する「料理人類学」を研究しながらインド料理を作り続けている。
食べ物を知ることはまさに人間を知ることに他ならず、食べ物を通して社会や文化が見えてくる。特にインドは食と社会の結びつきがとんでもなく根深い。この連載では旅を通じて知ったインド料理の魅力と、実際に家庭で作って楽しめるレシピを紹介していきたい。
インドにいる間試作ができず間が空いてしまったが、第二回はビリヤニの話をしたい。
8,300万皿のビリヤニ
日本では最近ビリヤニが大きな注目を集めていて、しばしトレンドにも入っているようだが、インドでもビリヤニの人気は衰えることを知らない。最近ではオンラインデリバリーが盛んで、注文してから届くまでが本当に速い。あるフードデリバリーサービスでは2024年には8,300万ビリヤニが注文されており、年間の数をならすと1秒に2皿はビリヤニが注文されている計算になる。

現在、イスラム教徒にとって神聖なラマダーンの時期を迎えている。ラマダーンは断食をする月として有名だが、全く何も食べないわけではない。日の出前と日没後は友人や家族と集まりたくさんのご馳走を食べるため、普段よりむしろたくさん食べて体重も増える。ムンバイのムスリム食が数多く集まるムハンマド・アリ・ロードなどのエリアでは、宗教関係なく多くの人々が美味しいものを求めて集まり、活気に満ちごった返していた。もちろんビリヤニも大人気。
ビリヤニの歴史はムガル帝国と深く結びついており、そもそもはムガルの宮廷料理として発展してきた。タミルのタラカパッティビリヤニやケーララのタラッセリービリヤニ、バンガロールのドンネビリヤニなど、バスマティライスを使わないものも多く存在する。中には芋や麺を使って作られる、「それってビリヤニなの!?」と驚くようなものもある。
ダムビリヤニの起源とムガル宮廷のキッチン
ビリヤニの代表ともいえる、層状に重なった「ダムビリヤニ」の調理法「ダム」は、鍋を密閉し弱火で蒸し焼きにする方法だ。パン生地を使って鍋の隙間を塞ぎ、炭火で上下からじっくり長時間弱火で蒸しあげる。そうやって作られるダムビリヤニはムガル宮廷のキッチンがルーツだという話がある。
ビリヤニのルーツについては諸説あるが、ペルシャからインドに伝わった米料理の「プラオ」がムガル帝国の宮廷でインドの調理法と合流し、各地に広まったという説が有力だ。第三皇帝アクバルの頃に文化的ピークを迎えたムガルの宮廷では毎日宴会が開かれていた。
キッチンではたくさんの料理人が雇われ、香り高いバスマティ米と肉を順番に層状に重ねて「ダム」する手法が確立された。このダム調理は合理的で、チームで分業し、短時間で、何百人分もの美しい見た目のビリヤニを作ることができた。層状に重ねることで見た目も美しく、味もひと口毎にランダムに変わり、風味も立体的に感じられる。

このムガルの伝統を色濃く残しているのが、インドのラグジュアリーホテル内にある[Dum Pukht]のような高級レストランだ。ここでは、当時の調理法やレシピを忠実に再現し、宮廷料理のエッセンスを体験することができる。店内は大理石と豪華絢爛な調度品で統一され、まるでムガル宮廷にタイムスリップしたような気分になれる。
前菜として「カコリカバブ」というパパイヤ酵素の力で肉を柔らかくしたカバブをいただく。続いて登場するラクナウ式のダムビリヤニは、ラム肉がしっとり柔らかく、一粒一粒のバスマティライスがしっとりとしていながらもほぐれるようなミルキーな口当たりがあった。両方ともとても柔らかく調理されているのだが、これは歯がない皇帝でも食べられるようにという配慮の結果らしい。


この店のビリヤニを食べたことで早くラクナウに行かなきゃと思ったのだが、まだ行く機会に恵まれていない。
忘れられないコルカタ、SABIR’Sのビリヤニ
ビリヤニといえば、ジャガイモとゆで卵が入る東インドのコルカタのビリヤニも有名だ。コルカタのビリヤニのルーツは先述したラクナウにあると言われる。大きな違いはジャガイモの有無で、ヨーグルトサラダのライタなどもつかないギー風味のあっさりとした味わいだ。なぜジャガイモが入るようになったのかは諸説あるが、単純にコルカタの人がじゃがいもが好きだからで、入っていると美味しいからだと思う。

いくつか食べ歩いたのだが、その中で一番印象に残っているのが[SABIR’S]のビリヤニだ。専門店というわけでもなく何か特別な演出があるわけでもない。だけどあの店のビリヤニは妙に心に残る味だった。ホワイトペッパーとメースを中心とした香り高いスパイスとバランスの取れた米の炊き加減、しっとりとしたマトンの柔らかさ。シンプルながらもミルキーな味わいがあり、また食べたいと思わせる何かがあった。
おうちで再現、フライパンコルカタチキンビリヤニ
ビリヤニは暗黙知が多くレシピで完璧に表現することは難しいが、家庭で再現しやすいようにチキンを使い、フライパンでつくるビリヤニのレシピを書いてみた。
本当はMittar Attarやケウラウォーター、ローズウォーターという香料が必須なのだが省いている。ビリヤニマサラはホワイトペッパーとメースを中心に組み立てるとよいが、今回は簡単にガラムマサラで代用しよう。


ビリヤニマサラの一例
◎材料(4人分)
チキンマリネ用フライドオニオン:
・玉ねぎ 150g(繊維に直角に薄切りハーフカット)
・揚げ油 適量(かぶるくらい)
具材:
・じゃがいも 2個(皮を剥いて半分に切り、水にさらす)
・ゆで卵 3個
チキンマリネ用:
・鶏もも肉(皮なし) 500g(大きめにカット)
・塩 5g
・ヨーグルト 75g
・ギー 小さじ1
・ニンニク・ショウガすりおろし 大さじ1ずつ
・ターメリックパウダー 小さじ1/2
・チリパウダー 小さじ1
・コリアンダーパウダー 大さじ1
・ビリヤニマサラ(またはガラムマサラ) 小さじ1
・青唐辛子(オプション) 1本(ちぎって加える)
じゃがいも・ゆで卵の下処理用:
・マスタードオイル 大さじ3
・メース 1片
・カルダモン 2粒
・ターメリックパウダー 小さじ1/2
・チリパウダー 小さじ1/2
・塩 1g
仕上げ用:
・クリーム(または牛乳) 大さじ2
・ギー 大さじ1
・サフラン ひとつまみ(50ccの水で煮出しておく)
米:
・バスマティライス 400g
・湯取り用のお湯 2L
・塩 茹でる水の1%
湯取り用スパイス(お茶パックに入れるとよい):
・シナモンスティック 2.5cm
・フェンネルシード 小さじ1/2
・グリーンカルダモン 3粒
・ブラックカルダモン 1粒
・スターアニス 1個
・ブラックペッパー 10粒
・ベイリーフ 1枚
◎下準備
・バスマティライスを2回洗い、30分以上浸水させる。
・玉ねぎ150gを繊維に直角に薄切りし、低温の油でじっくりと揚げてフライドオニオンを作っておく。色が余熱で変わるので早めにあげる。最初に炒めてもいいが、フライドオニオンは肝なので別で揚げる方がよい。
・鶏もも肉を大きめ(70~80g)にカットし、マリネ用の材料(塩、ヨーグルト、ギー、GGP、ターメリックパウダー、チリパウダー、コリアンダーパウダー、ビリヤニマサラ、青唐辛子、フライドオニオン)を混ぜ合わせ、30分以上漬け込む。
・フライパンにマスタードオイルを熱し、メースとカルダモンを加えて香りを出す。水にさらしておいたじゃがいもの水気を拭き取り、ターメリックパウダー、チリパウダー、塩をまぶしてフライパンで表面を焼き、50%程度火を通す。火が通りにくいので蓋をして10分程度弱火で少し蒸し焼きにするとよい。同じフライパンでゆで卵にも軽く焼き色をつける。
・サフランひとつまみ(30~40本程度)を50ccのお湯で煮出しておく。
◎調理
①グレイビーの調理。フライパンから一旦じゃがいもとゆで卵を取り出して焼いた油をそのまま残す。マリネしたチキンを加えて表面に軽く焼き色がつくまで動かさず加熱。水50cc、牛乳(またはクリーム)、ギーを加えて混ぜ合わせる。卵、じゃがいもを戻し、蓋をして弱火で10分ほど煮る。

②バスマティライスの調理。グレイビーと並行して、大きな鍋に浸水前の米の5倍量以上の湯を沸かし、1%の塩とお茶パックに入れたスパイスを加える。浸水しておいたバスマティライスの水を切って加え、一旦沸騰したら弱火で静かに茹でる。約5分間茹でて50%程度の硬さになった時点で半分を取り出し、ざるでよく水を切ってからチキンの入ったフライパンに加え、半炊きの米でスープを覆い尽くすようにする。残りの米は95%程度まで茹でてからザルにあげ、フライパンの米の上に蓋をするように重ねる。

③ダム(蒸らし)工程。サフランを煮出した水をフライパン全体に回しかける。蓋をしっかりと閉め、一旦中強火で加熱し、しっかりフライパンが温まったらごく弱火で20分間加熱する。火が強すぎると焦げるので間に鉄板を挟むのが理想。
④仕上げ。火を止め、蓋をしたままさらに10分間蒸らす。木べらではなく柔らかいタイプのしゃもじを使う。米を折らないように横から差し入れて盛り付ける。

ビリヤニを通じて触れるインドの多様性
ビリヤニはムスリムの料理がルーツではあるが、宗教も国籍も関係なく楽しまれている。ビリヤニは、実は飲食店で最高の状態で提供することが難しく、自分で炊いた方がおいしい状態で食べやすい。複雑な調理工程と繊細な火加減が求められるため上達までなかなか時間がかかるが、うまく仕上がった時の喜びはひとしお(私は20代最後の夏をずっとダムして過ごしました)。パーティーにも持ってこいなので、時間があるときに作ってみては。

- Researcher of South Asian Food Anthropology
カレー哲学 / Curry Philosopher
カレー哲学者/南アジアの食の人類学研究者(の卵)。「日本にインドを作る」ことを目指すインド料理グループ「東京マサラ部」首謀。カレーにまつわる同人誌『カレーZINE』、インドパンのアナログカードゲーム『ATSU ATSU!! Parotta』、『TOKYO MASALAND』など、インド料理関連のプロジェクトを手掛ける。
X @philosophycurry
note @philosophycurry


 Curry Philosopher
Curry Philosopher 
 RiCE.press
RiCE.press 


 Hiroshi Inada
Hiroshi Inada 

 Kohei Yamaguchi
Kohei Yamaguchi 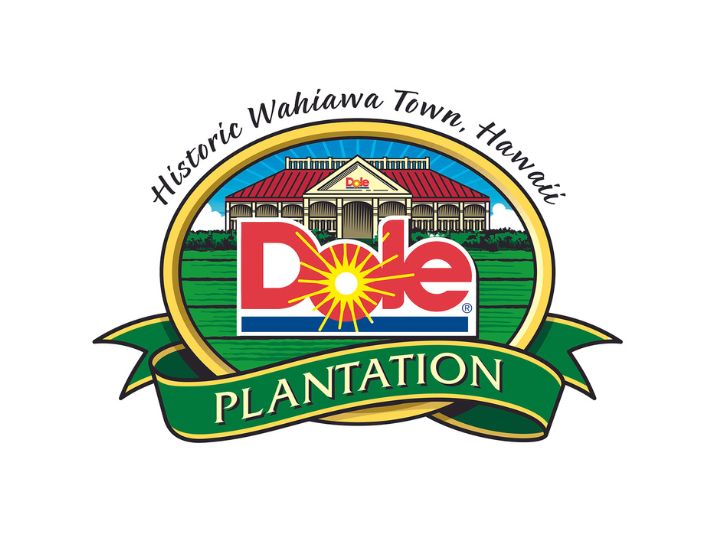
 So Igarashi
So Igarashi 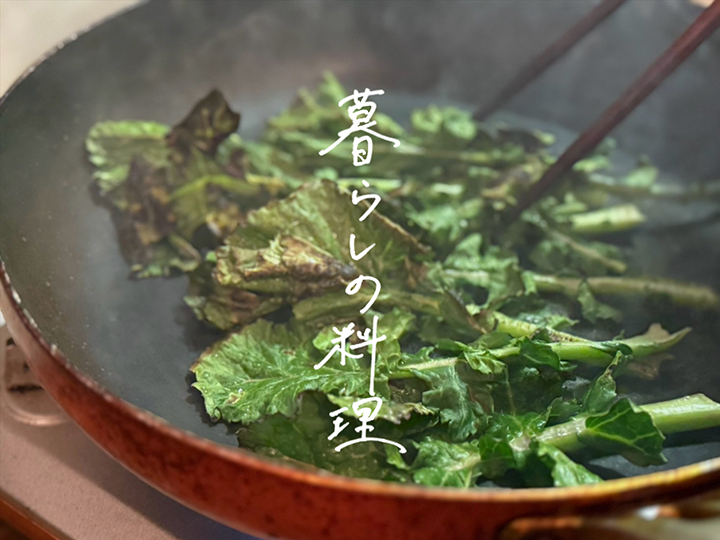
 Ryuichi Namihira
Ryuichi Namihira